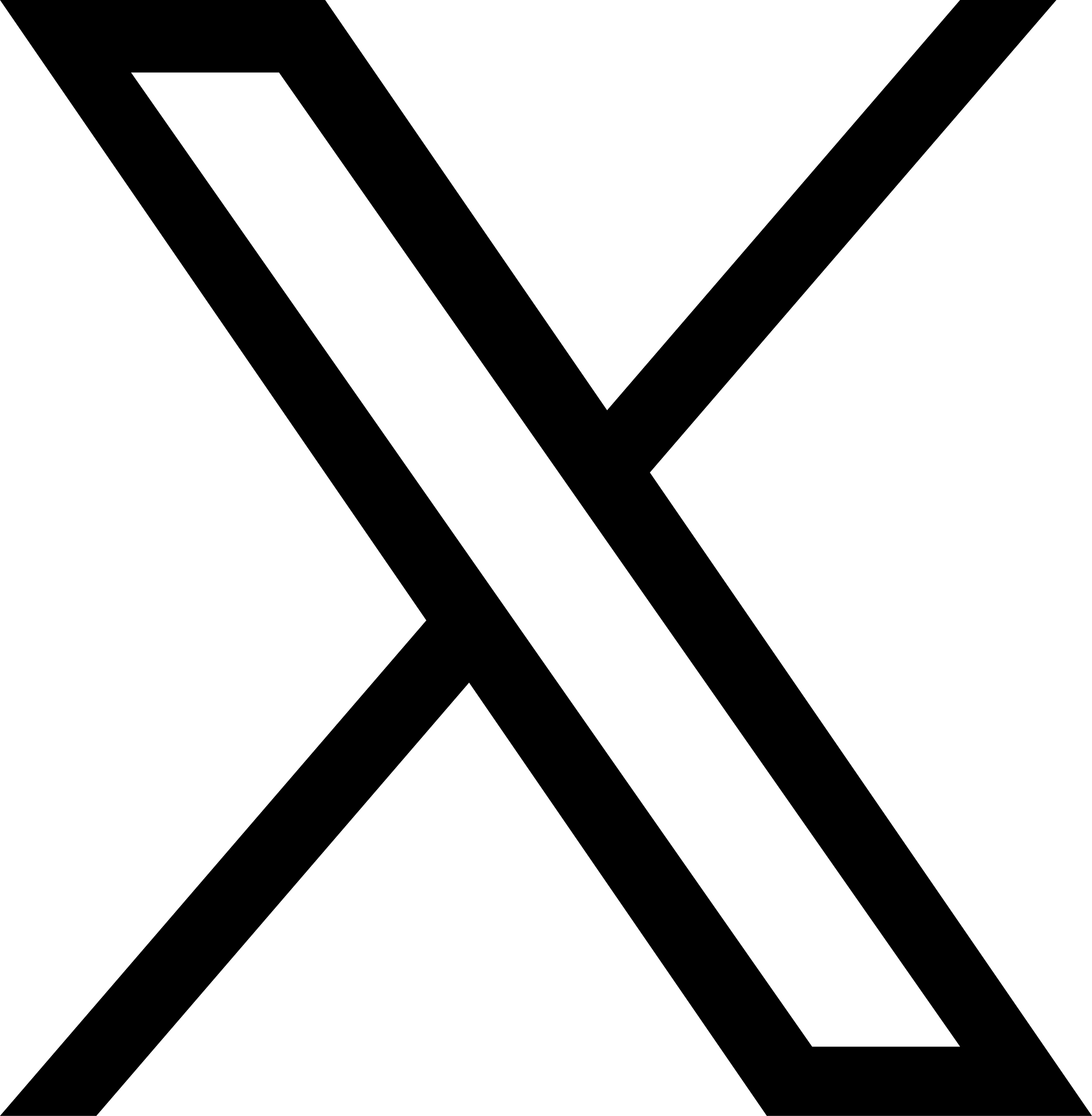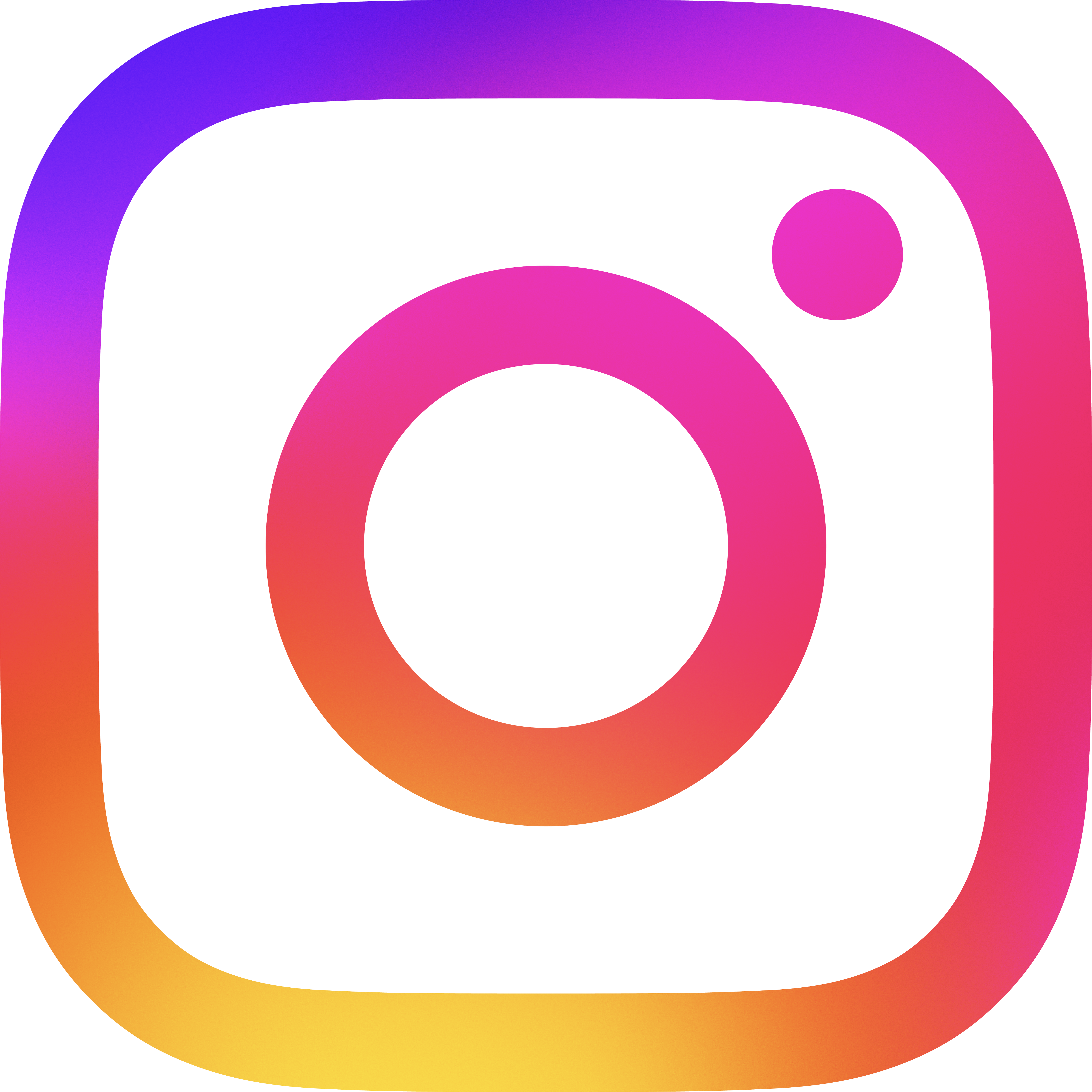〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1
概要

1980年以降、日本人の死因の第1位をがんが占めています。「国民病」とも言われるがんへの対策として、早期診断、ゲノム医療、ロボット手術、分子標的治療や免疫療法を含めた薬物療法などの開発・改良がなされ、がん医療は急速に進歩しています。臨床腫瘍センターは、医療の進歩にあわせて悪性腫瘍(がん)に総合的かつ重点的に対応するための司令塔の役割を担う診療科横断的な組織です。がん診療連携拠点病院である愛知医科大学病院におけるがん診療の中心的な役割を担い、地域連携やがん相談などを含め、愛知医科大学病院ならびに地域のがん診療のまとめ役を務めています。
腫瘍内科部門は遺伝子解析を含めたがん薬物療法を、腫瘍外科部門は手術が関わる腫瘍(がん)の集学的治療を、外来化学療法部門は実際のがん薬物治療をそれぞ司令塔として担当します。がん薬物療法の進歩はめざましく,従来の細胞障害性抗がん薬に加えて,次々と新しい分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬が登場し,さらにがん組織や血液を用いたがん遺伝子パネル検査が保険適応となり、個人の特徴に合わせた治療を強い副作用なく行えるようになりました。がん対策基本法の基本理念の一つである、本人の意向を尊重した治療の選択を尊重し、標準治療だけでなく、高齢者や臓器機能低下など患者の特性に合わせた治療を推進します。
重複癌や原発不明癌、希少がん、進行癌に対する多科共同手術や重篤な合併症のある患者さんの治療方針など、ひとつの診療科だけでは判断に迷う症例に対して随時キャンサーボードを開催し、複数診療科の医師や看護師、薬剤師などが集まって相談し、解決法を提案しています。がん救急や有害事象対策には全診療科が関わっています。
臨床腫瘍センター運営委員会を毎月開催し、がんに関わる全診療科と院内の関係者が集まり、がん薬物療法やゲノム診療、思春期・若年成人患者さん(AYAと略します)のがんを含めたがん相談や地域連携の実績と問題点の報告、がん薬物療法委員会としてがん治療レジメンの審査を行っています。
診療部門からのごあいさつ

部長
久保昭仁
愛知医科大学病院はがん診療連携拠点病院として地域のがん診療における中心的な役割を果たしています。臨床腫瘍センターは当院におけるがん診療のさまざまな課題に対応するため2012年に設置されました。腫瘍内科、腫瘍外科、外来化学療法の3部門で構成され、診療科横断的にがん診療の進歩・発展のために尽力しています。
主な対象疾患
呼吸器がん
肺がん、胸膜腫瘍、縦隔腫瘍
消化器がん
食道がん、胃がん、大腸がん、胆膵がん
血液がん
白血病、悪性リンパ腫、その他の造血器腫瘍および類縁疾患
診療・治療実績
| 外来診療 | 月・火・木・金 |
|---|---|
| がん薬物療法委員会 | 毎月1回 |
| キャンサーボード 開催 | 毎月1~2回 相談症例に応じて随時開催 |
| 外来化学療法件数 |
がんゲノム診療について
日本人の死因第1位である「がん」への対策の一環として2019年に保険診療でのがんゲノム医療が始まりました。「がんは遺伝子の病気」と言われるとおり、がんの多くは遺伝子の異常が原因で、一部には遺伝するがんもあります。がんの組織や血液を用いて数百種類の遺伝子を調べる「がん遺伝子パネル検査」によって、その結果から個々の患者さんに合わせた治療などが提案できるようになりました。2025年4月現在ではがん組織を用いるがん遺伝子パネル検査が3種類、血液検体を用いるものが2種類あり、それぞれの患者さんに最も適した検査をおこなっています。2025年3月には造血器腫瘍遺伝子パネル検査が保険適用となりました。
愛知医科大学病院では、遺伝性乳癌卵巣癌症候群 (HBOC)、家族性大腸ポリポーシス、多発性内分泌腫瘍症 (MEN)、リンチ症候群、リ・フラウメニ症候群、神経線維腫症などの遺伝性腫瘍(がん)に関しても、各診療科、ゲノム医療センター、臨床遺伝診療部が連携して、カウンセリングや専門的な治療を行っています。
関連リンク
キーワード
キャンサーボード、がん遺伝子パネル検査、薬物療法
連絡先
- TEL
- 外線 : 0561-62-3311(代表)
- 内線 : 36500 31外来 または 内線:36310 30外来化学療法室