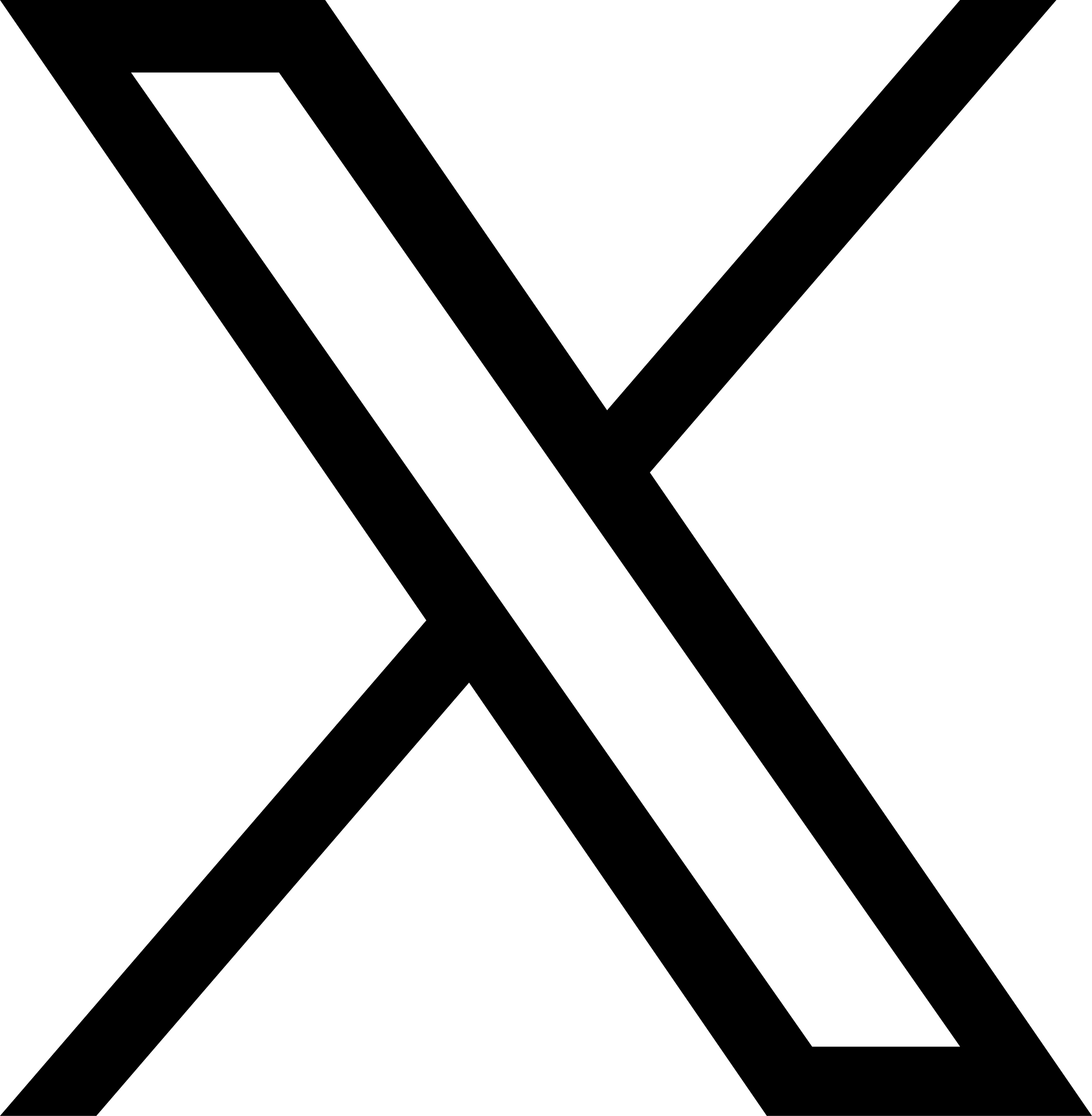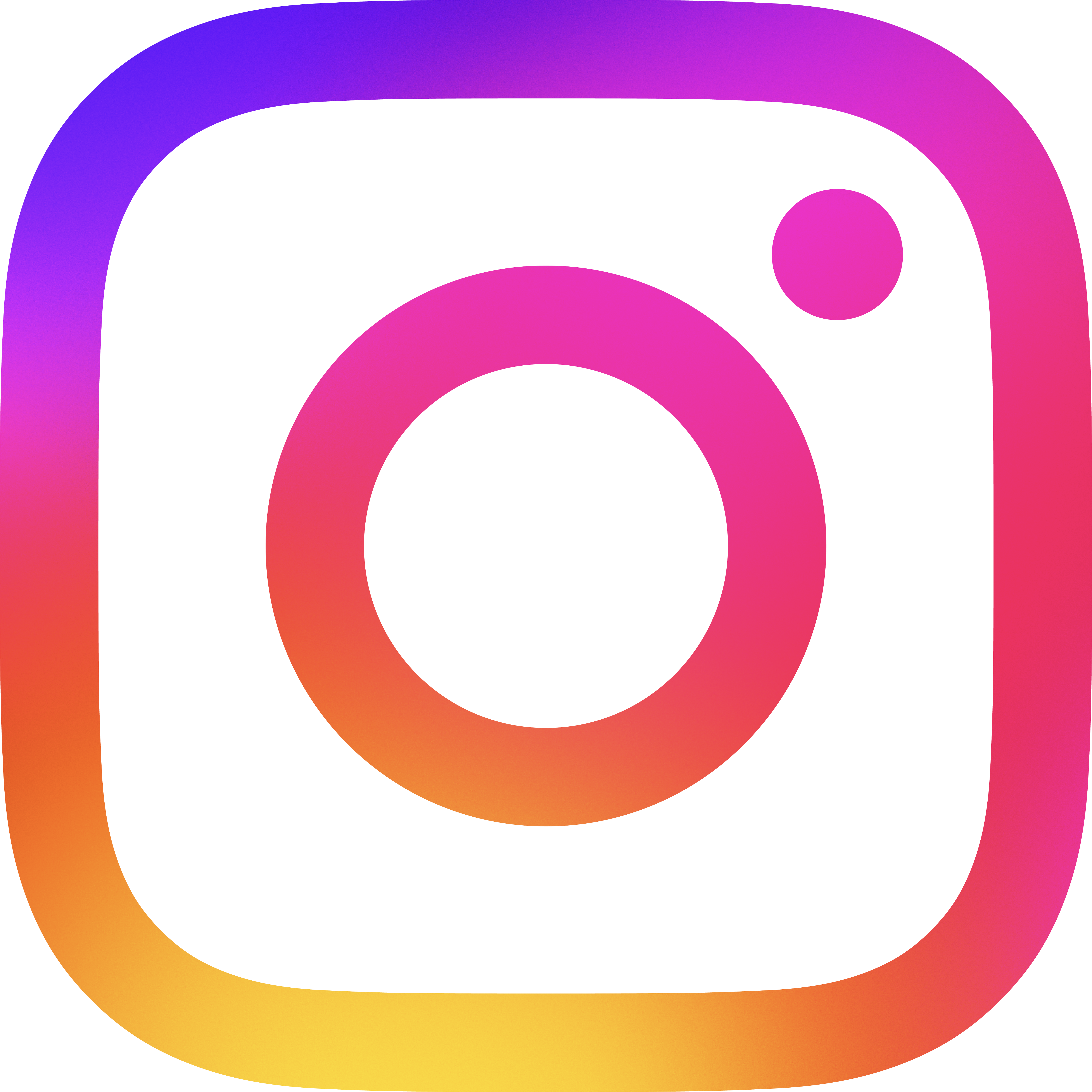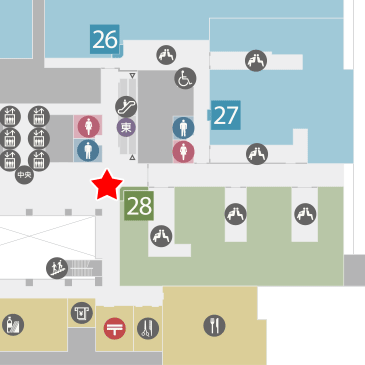〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1
概要
肺胞蛋白症(はいほうたんぱくしょう)は、肺の中に、サーファクタントという物質が過剰に貯留してしまう、たいへんまれな病気(希少疾患)です。2019年本邦での疫学調査では、人口100万人当たりの有病率が26.6人と報告されました。厚生労働省の指定難病にも含まれています。
肺胞蛋白症では、肺の中にサーファクタントが貯まるため、胸部CT画像で、両肺に陰影が映ります。「メロンの皮状」「すりガラス陰影」などと表現されるのが特徴的な陰影です。肺胞蛋白症を疑った場合は、気管支鏡(内視鏡)検査を行い、生理食塩水を注入して気管支肺胞洗浄(BAL)を追加します。この洗浄液が、白く濁っている(「米のとぎ汁様」「milky(ミルク様)」などと表現されます)ことで、「肺胞蛋白症」の診断に至ります。
サーファクタントを処理する「肺胞マクロファージ」という免疫細胞の数が減る、うまく働けなくなるなどの理由により、病気が発症します。肺胞蛋白症例の90%以上を占めるのが、自己免疫性肺胞蛋白症(APAP)です。肺胞マクロファージの分化や機能を維持するために必要な、granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)という物質に対する自己抗体(抗GM-CSF抗体)が作られることにより発症します。採血検査で血清中の抗GM-CSF抗体を調べることで診断できます。自己免疫性の他には、血液疾患や免疫疾患に伴う続発性(ぞくはつせい)肺胞蛋白症、GM-CSF受容体の遺伝子異常などにより発症する先天性・遺伝性肺胞蛋白症もあります。
病状は、軽症から重症まで様々です。軽症の方は、通常は経過を観察していきます。重症の方に対しては、全身麻酔の人工呼吸器下で、肺に生理食塩水を注入して貯留したサーファクタントを洗い流す「全肺洗浄(WLL)」という治療法があります。自己免疫性肺胞蛋白症の治療薬として、令和6(2024)年から、GM-CSF製剤サルグラモスチム(サルグマリン®)吸入療法が新たに保険収載されました。
愛知医科大学病院では、肺胞蛋白症の病状に応じて、全肺洗浄やサルグラモスチム吸入療法を行っています。
診療部門からのごあいさつ

部長 伊藤理
愛知医科大学病院呼吸器・アレルギー内科では、これまで多くの肺胞蛋白症患者さんの診察・治療を行い、他施設からのコンサルテーションにお応えしてまいりました。
このたび、令和7(2025)年5月1日より、新たに「肺胞蛋白症センター」を開設いたしました。患者さん、医療機関の方々に今後益々貢献できるよう、努力してまいる所存です。
主な対象疾患
主な対象疾患
- 自己免疫性肺胞蛋白症(APAP)
- 続発性肺胞蛋白症
- 原因不明の肺胞蛋白症
- 肺胞蛋白症の後遺症
高度な専門医療
高度な医療
GM-CSF(サルグラモスチム)吸入療法
全身麻酔下での全肺洗浄 (重症例ではECMO(エクモ)を併用します)
診療・治療実績
全身麻酔下での全肺洗浄(麻酔科・心臓外科・血管外科と連携します)
GM-CSF(サルグラモスチム)吸入療法
キーワード
自己免疫性肺胞蛋白症 (APAP),全肺洗浄 (WLL),GM-CSF吸入療法,気管支肺胞洗浄(BAL)
医療連携について
紹介状をお持ちの場合、新規の肺胞蛋白症患者さんに関しましては、
- 金曜午前(伊藤理)
- 水曜午前(田中博之)
当日の予約が無くても診察いたします。