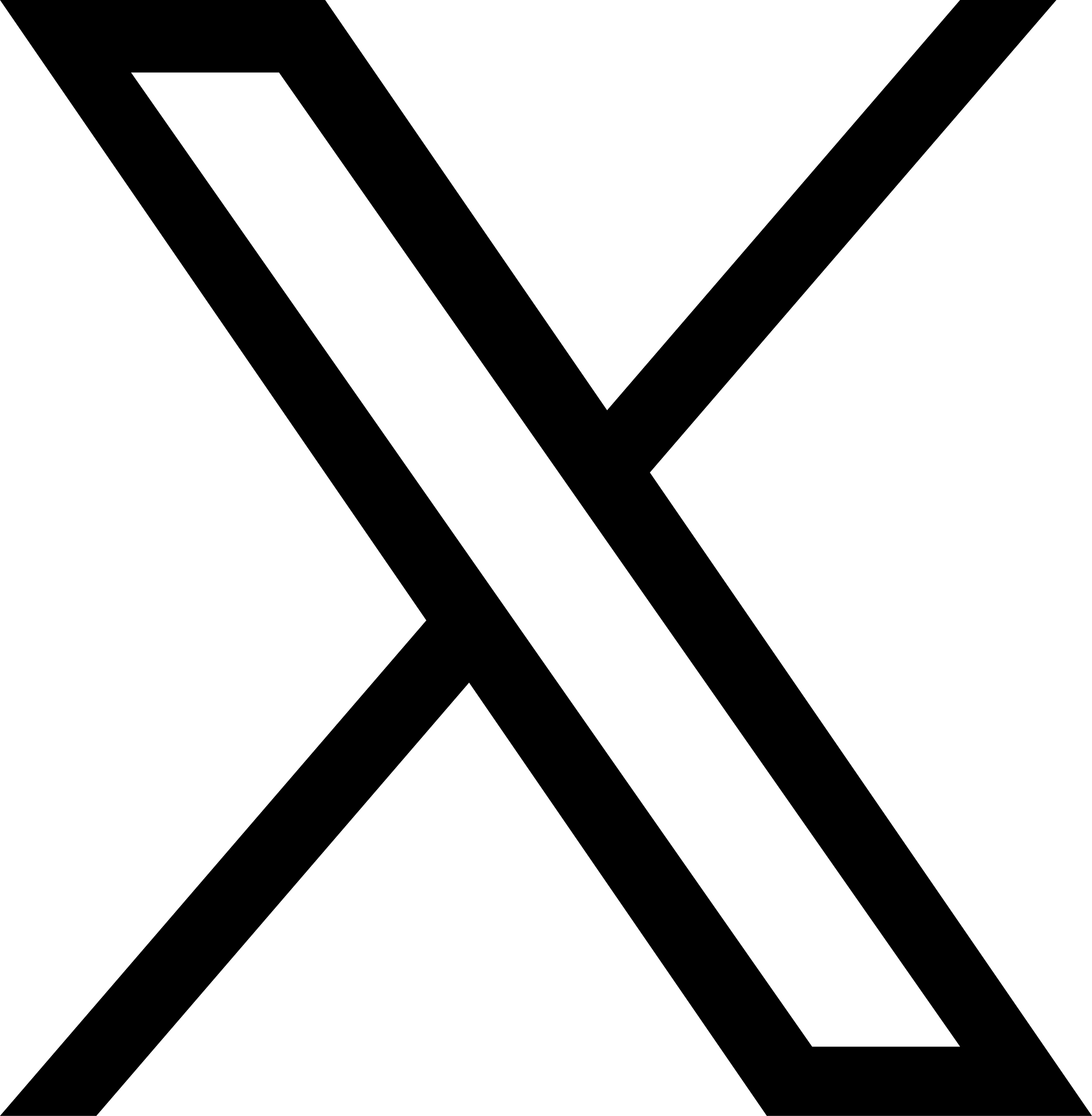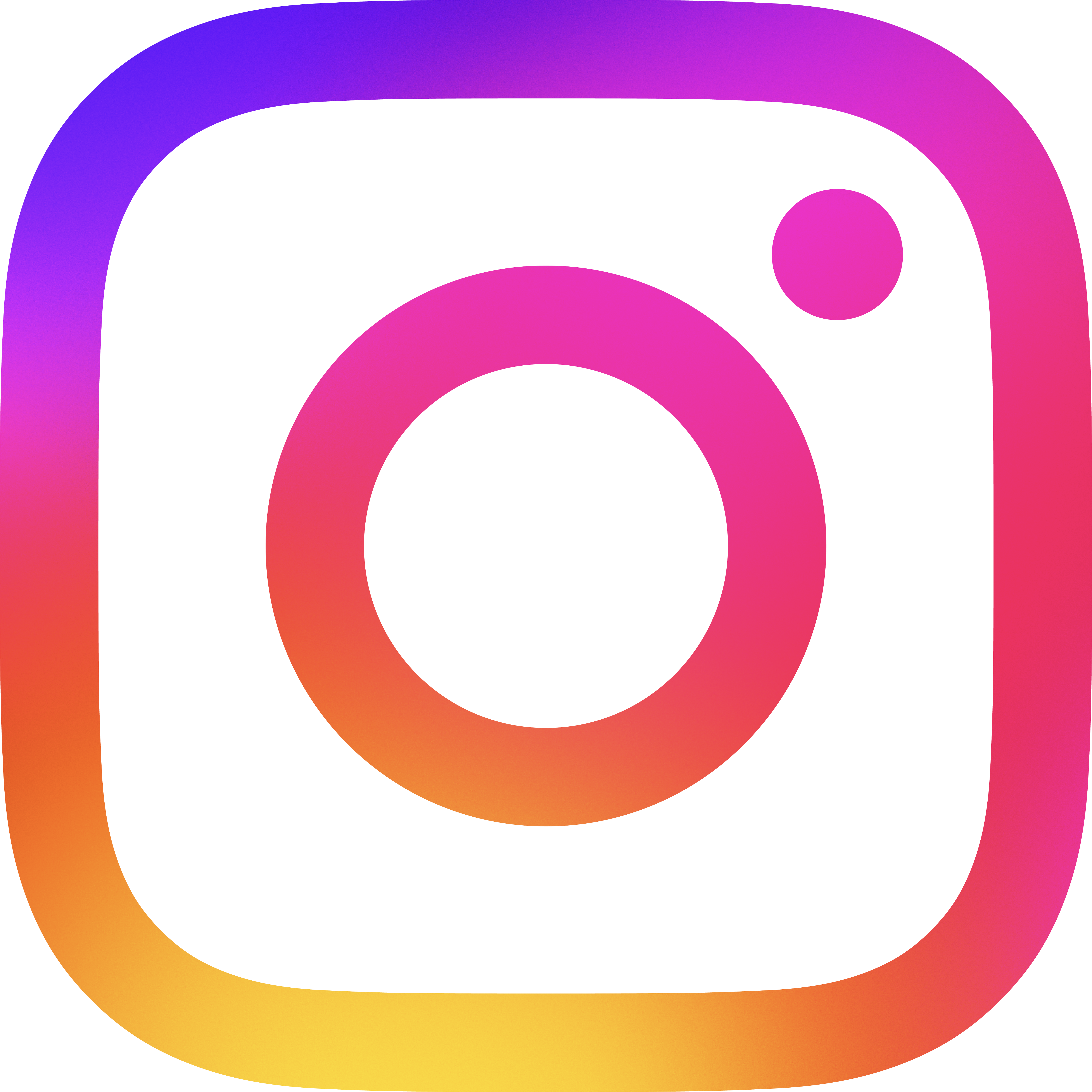〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1

神の手にこだわらない心臓外科医
松山 克彦 (マツヤマ カツヒコ)
心臓外科 平成27年9月1日就任
| 外来担当日 | 火曜日 |
|---|
| 専門領域 | 成人心臓大血管全般(虚血性心疾患,弁膜症,大動脈疾患) |
|---|---|
| 認定医・専門医等 |
|
診療についての抱負
座右の銘
今後,戦後最大の高度高齢化社会を迎える中,心臓,大血管疾患がさらに増えることが予想されます。当科では,虚血性心疾患,弁膜症,大動脈疾患と成人心臓血管外科領域を幅広く診療しています。急性心筋梗塞や不安定狭心症などの急性冠症候群や,急性大動脈解離や大動脈瘤破裂などの急性大動脈症候群に対しても昼夜を問わず24時間体制で対応しています。患者さんの状態に応じ,ご家族と十分なインフォームドコンセントのもと,患者さんにとっての最善の治療を行うようにしています。当院はハイブリッド手術室を有しており,心臓手術の低侵襲化を目指します。具体的には小切開,および,内視鏡を使用した手術,および,将来的には経カテーテル大動脈弁置換術もおこなっていきたいと考えております。
前赴任地は,新宿駅と東京都庁が目と鼻の先にあるまさに東京都心に位置した東京医大病院で勤務させていただきました。ここで培いました経験を活かし,大学病院として最先端の医療を志し,また,地域医療に力を注ぎ,微力ながら貢献したいと思う所存です。
学歴・職歴等
| 昭和60年 4月 | 福井医科大学医学部医学科入学 |
|---|---|
| 平成 3年 3月 | 福井医科大学医学部医学科卒業 |
| 平成 3年 5月 | 医師免許取得(医籍登録第336903号) |
| 平成 3年 6月―平成 4年 3月 | 福井医科大学医学部研修医(第2外科学講座) |
| 平成 4年 4月―平成 6年 3月 | 天理よろづ相談所病院医員(心臓血管外科) |
| 平成 6年 4月―平成 6年 5月 | 福井医科大学医学部医員(第2外科学講座) |
| 平成 6年 6月―平成 7年 4月 | 福井医科大学医学部助手(第2外科学講座) |
| 平成 7年 5月―平成 9年 3月 | 医療法人林病院医員(外科) |
| 平成 9年 4月―平成15年 3月 | 天理よろづ相談所病院医員(心臓血管外科) |
| 平成 9年12月 | 博士(医学)学位取得(福井医科大学) |
| 平成15年 4月―平成15年 9月 | 福井心臓血管センター福井循環器病院医員(心臓血管外科) |
| 平成15年10月―平成16年 6月 | 名古屋大学医学部医員(胸部外科) |
| 平成16年 7月―平成16年12月 | 中部労災病院副部長(心臓血管外科) |
| 平成17年 1月―平成21年 7月 | 中部労災病院部長(心臓血管外科) |
| 平成21年 8月―平成23年 3月 | 岐阜県立多治見病院医長(心臓血管外科) |
| 平成23年 4月―平成23年 7月 | 岐阜県立多治見病院部長(心臓血管外科) |
| 平成23年 8月―現在 | 東京医科大学病院准教授(心臓血管外科) |
| 平成27年 9月―現在 | 愛知医科大学 医学部 外科学講座(心臓外科) 教授 |
診療実績
過去6年間の執刀数
| 虚血性心疾患 | 230 例 |
|---|---|
| 弁膜症手術 | 190 例 |
| 大血管手術 | 110 例 |
フォトアルバム




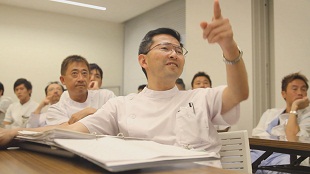

インタビュー
ご専門分野について教えてください
成人一般の心臓手術,心筋梗塞,狭心症に対する冠動脈バイパス手術,弁膜症に対する僧房弁形成術あるいは僧房弁置換術,大動脈解離,大動脈弁形成に対する手術,一部ですが先天性の手術もあります。また,複雑な手術はないですが,一般的な小児手術もあります。
心臓疾患で近年多いのは,心臓弁膜症です。心臓弁膜症というのは,血流を一定方向にするための「弁」が逆流を起こしたり,狭くなって心臓に負担がかかるというもので,そうなると息切れを起こして心不全症状をきたすか,不整脈が起こりやすくなるので,それによって脳梗塞が起こることもあります。
この心臓弁膜症の治療は大きく分けて,2つあります。1つ目は,自分の弁を残して,弁を形成する弁形成術というものです。2つ目は自分の弁を取ってしまい,人工弁に替えるという2つの方法です。基本的には,まず自分の弁を残す弁形成術を目指します。
先生が勧める低侵襲手術とはどのような手術ですか
大きく分けて2つあり,傷を小さくする手術であり,患者さんの負担を少なくする手術です。傷を小さくするためには,狭い視野で手術をしなければならないのでリスクは高くなりますが,患者さんにとっては術後の回復が早かったり,痛みが少ないというメリットが生まれます。
バイパス手術に関しては,従来は大きく開胸していましたが,最近はコンパクトになっています。今までは,まっすぐ大きく切っていたものを,今はたとえば,上半分や下半分だけを切って手術する。あるいは,ミックス手術といって右の僧房弁なら右から開胸,バイパス手術なら左から胸の下の方から10センチくらいの傷で手術をする方法があります。
開胸の場合は,基本的には骨は切りません。肋間という肋骨と肋骨の隙間があるので,そこを広げてそのスペースを利用して手術をします。
カテーテル治療の内容を教えてください
人工弁(生体弁)を装着したカテーテルを足の付け根から挿入し心臓まで持っていき,大動脈弁置換術,留置術という意味合いの手術を行います。術後,患者さんは翌日から歩けるようになり,3~4日で退院できます。その点で,今までの心臓手術とは全く異なります。毎年,ヨーロッパなどでは,新しい器具が誕生しており,人工弁も毎年,最新のものが学会で発表されるなど進歩しているので,こちらもそれに乗り遅れないように勉強しています。しかし,なんでも新しければいいというものではなく,今までの治療法と比べてどちらがいいかと十分に見極めたうえで,患者さんのためになるものを採用していきたいと考えています。
ミックス手術の現状を教えてください
シンプルな手術は問題ありませんが,動脈硬化数が高い方や手術のリスクが高いと思われる方,複雑な手術が必要な方には従来通りの手術になります。カテーテル手術も大きく捉えると,ミックス手術のジャンルに含まれます。手術は低侵襲手術で行うため,左の開胸で行う場合と,カテーテルだけの場合と2通りあります。
これは,循環器内科の先生と放射線科,血管内科の先生と一緒に手術をします。
ミックス手術は,視野が狭い状態の中,内視鏡を使って,画像をみんなで共有しながら,見えないところで手術をします。先が見えないことから,いろいろなトラブルの可能性があります。そのため,自分以外の心臓外科の先生2~3人,麻酔科の先生,臨床工学技士さん,人工心肺をまわす技師さん,器械出しと外回りを担う看護師さんら約10人程度のスタッフが関わって手術を進めます。手術前には,そのメンバーが集まって手術の内容を細かなところまで打ち合わせをし,予想される事態とその対応法などの事前に取り決めをして手術に臨みます。
医学の道に進んだきっかけは?
祖母が亡くなって,近所に医師が死亡確認をしたのを見て医師という職業に憧れました。
心臓外科を選ばれたことについてどうお考えですか
心臓外科ほど,やりがいのある診療科はないのではないかと思っています。このままでは亡くなるという患者さんを,手術によって治すことができるので,そういう意味でやりがいが大きいですね。苦しんでいた患者さんが元気になって帰られる瞬間は,医師をやっていてよかったと思います。
座右の銘や好きな言葉はありますか
私は,どちらかというと,せっかちな性格なので常に「急がば回れ」と自分に言い聞かせています。「同じような手術でも,患者さんによって状態が異なり,思わぬことが起こることもある。その時に,原点に立ち返って,これはどうしてこうなったのかと,振り出しに戻って考える。それでまた手術を進める」ということを普段の手術の時に心がけています。思わぬトラブルが発生した時も「急がば回れ」とみんなで考えて,ジャッジするようにしています。心臓手術は時間が長いので,何秒でジャッジするという訳ではなく,1~2分は考えます。場合によっては,縫合してももう一度,やり直すということもありますよ。
今後の愛知医大の心臓外科で目指すものは?
患者さんにとって,いちばん負担の少ない手術を目指したいと思います。具体的には,低侵襲手術ということになるでしょう。中でも今後ますます増えるのはカテーテル治療だと考えられますが,カテーテル治療と心臓手術を組み合わせたハイブリッド手術も1つの低侵襲手術だと思います。そういうものも積極的に取り入れて,患者さんにとっていちばんいい治療方法,負担の少ない治療を目指していきたいですね。
他の診療科と比べて,心臓外科は特異ではないか
心臓を止めて行う手術が多いので,一歩間違えると死につながります。リスクが高い手術であると思います。逆に,このまま何もしないと亡くなるという人が手術をすることで劇的によくなって,元気に帰れるというのは他の科にはないやりがいのあるところだと思います。
これまでのキャリアの中でエピソードがあれば教えてください
大動脈解離の手術は,長時間を要する手術ですが,ある時の手術は予想をはるかに上回る36時間を要しました。周りは,みんなへとへとで,手術室の廊下で寝てしまったことがありました。
患者さんへのメッセージをお願いします
愛知医科大学の心臓外科は,循環器内科との連携によって患者さんやご家族の背景を考慮し,医学的な面だけではなく社会的な面も考慮して治療方針を決めていきます。