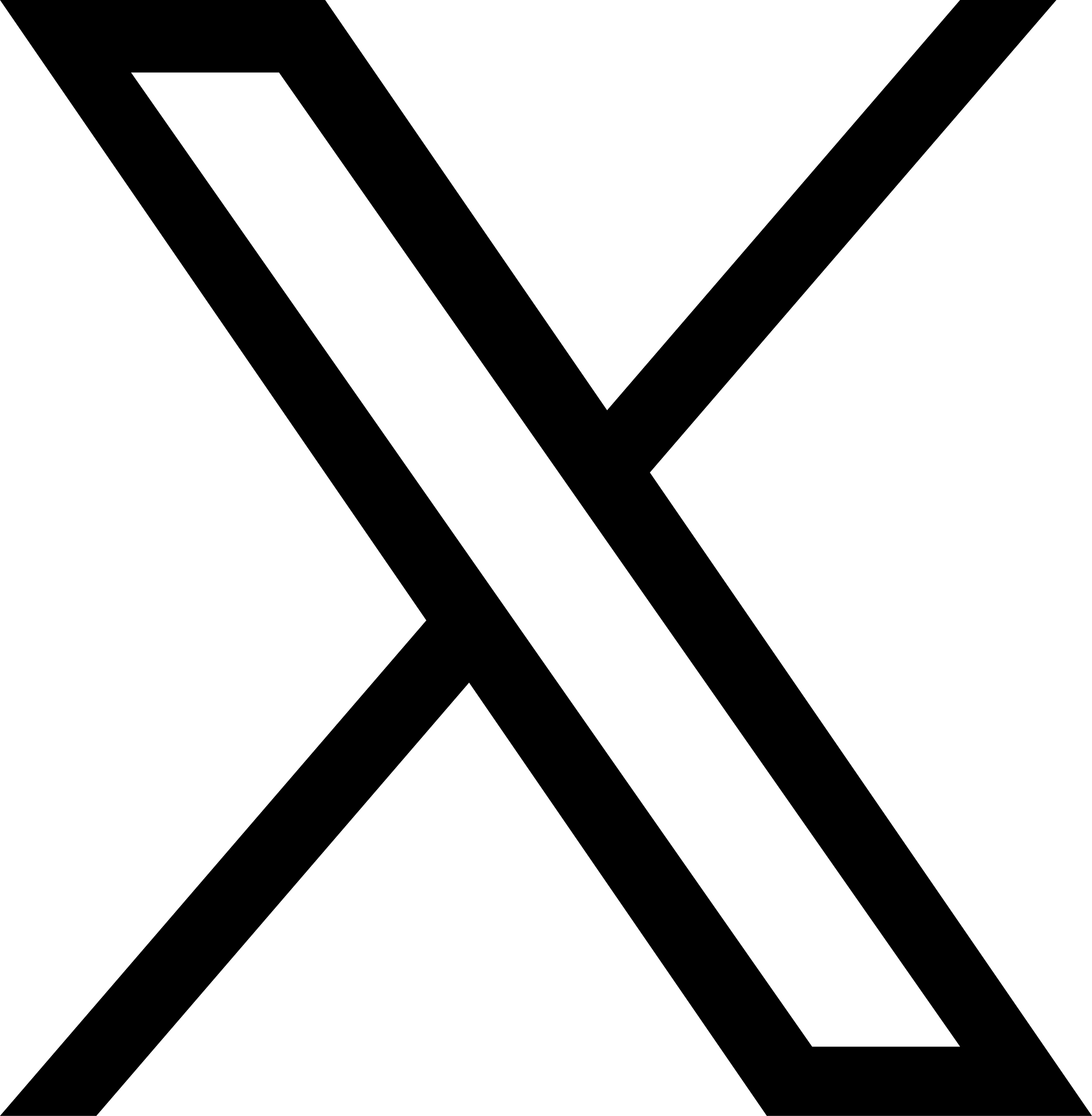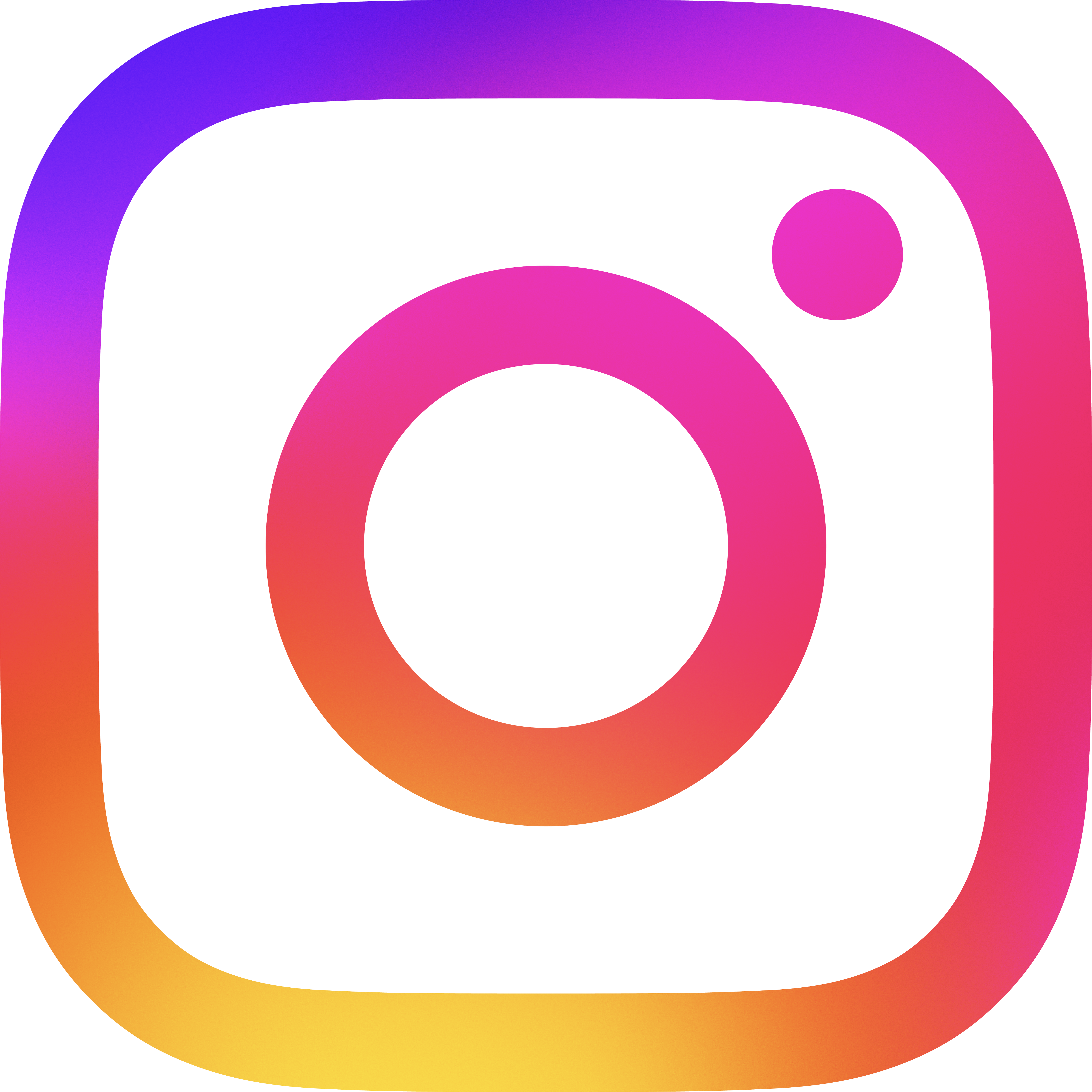〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1
概要
愛知医科大学病院輸血部は1997年に設立され,中央診療部門の一部として,臨床検査技師9名(日本輸血・細胞治療学会 認定輸血技師5名)と輸血認定医1名で各診療科と協力しながら輸血診療の全般を担っています。当院は急性期病院であるため,年間に延べ約6,000人の患者さんが,輸血を受けられ,救急搬送患者や緊急手術の輸血にも24時間体制で迅速に対応しています。
2024年度は赤血球製剤12,388単位,新鮮凍結血漿7,257単位,濃厚血小板24,830単位を使用し,自己血採血は421件行いました。検査件数は血液型検査19,099件,交差適合試験5,145件,不規則抗体検査14,110件,その他の輸血関連検査1,119件にまでのぼります。
当院の特色としてNICUを有しているため,新生児の輸血や交換輸血,あるいは神経,肝疾患患者における血漿交換にも対処しております。輸血療法においては製剤による副反応が発症する場合があり,特に頻度が高い血小板製剤においては,日本赤十字血液センターへ発注・取寄せした洗浄血小板にて副反応予防に効果を挙げています。関連業務として造血幹細胞移植のための末梢血幹細胞採取を患者さん及びドナーさんから実施しています。
私たちは知識,技術の向上のため,国内あるいは海外の学会や研究会に積極的に参加,発表し,さらに学外からの研修生の受け入れも行っています。輸血療法は患者さんの命を助ける大切な治療法でありますが,血液型の間違い,人為的ミスなどによっては致死的になる恐れがあります。愛知県赤十字血液センターや近隣病院と密に連携を取りながら,安全で質の高い医療を目指し,正確で慎重な検査,製剤管理及び治療に努めております。
ごあいさつ

部長 中山享之
輸血医療は,不足した血液成分を血液製剤により補充する治療法で,重症患者の救命にも欠かせません。一方,血液製剤は善意の献血に基づく限られた血液を元に作られるため,輸血医療には適切な使用法が求められます。愛知医科大学病院輸血部は,輸血に関連する業務全般を管理・運営し,安全で効果的な輸血医療を提供しています。自己血輸血を含む安全な輸血の実践にも積極的に取り組み,細胞治療にも取り組んでいます。輸血部スタッフは,高度な技術と知識を持ち,安全かつ効果的な輸血医療を提供するよう努めています。
業務案内
血液製剤の管理,調製業務

血液製剤の無菌的充填
輸血が必要になったとき,安心して輸血を受けていただけるように,輸血用血液製剤(赤血球液,新鮮凍結血漿,濃厚血小板など)の在庫を管理しています。日本赤十字血液センターへの発注業務から最適な条件での保管管理,輸血後GVHDを防止するための製剤への放射線照射まで一元化して管理しています。また2014年5月から,アルブミン製剤やガンマグロブリン製剤などの血漿分画製剤についても在庫管理,発注業務,保管管理などの一元管理を開始しました。調整業務として,新生児の輸血に際しては,血液製剤の無菌的な注射器への補充を行っています。さらに,新鮮凍結血漿からクリオプレシピテートを院内調整し,大量出血時の凝固障害に対応しています。
輸血関連検査業務

血液型検査

全自動輸血検査装置
輸血に際し必要な血液型検査など,主な検査として次のように実施しています。
ABO血液型
採血間違いによる誤判定を防止するため,別採血の血液を用いて2重に検査させていただきます。また,少し通常のABO血液型と反応性が異なっている場合(亜型など)であっても,輸血時に副反応が起こらないように,唾液の検査や血液型転換酵素活性を測定するなどして血液型を決定します。
Rh血液型
Rh陽性,陰性の判定(D抗原を持つ人をRh陽性,D抗原を持たない人をRh陰性と呼びます)だけでなく,必要な場合はD抗原以外のRh関連抗原であるCcEe抗原の判定も行います。
その他の血液型検査
ABO,Rh以外の血液型検査です。現在,血液型は40種類ほど知られていますが,輸血時に問題になりやすい,ルイス血液型,キッド血液型,ダフィー血液型,MNS血液型などを実施しています。
不規則抗体検査
輸血による溶血性副反応を防止するために,輸血が予定される患者さんに対し不規則抗体スクリーニング検査を実施します。なお,スクリーニング検査が陽性となった場合は,どの血液型に対する抗体かを判別するために不規則抗体同定検査を実施します。
※不規則抗体とは,ABO以外の血液型に対する抗体で,妊娠や輸血により産生されることがあり,場合によっては溶血性副反応の原因となります。
交差適合試験
赤血球液など赤血球成分を輸血する際に,患者さんの血液と実際に輸血する製剤を試験管内で混合し,溶血や凝集反応が起こらないことを調べる検査です。輸血する製剤が患者さんと適合することを確認するために行います。不規則抗体検査と同様に輸血による溶血性副反応を防止する目的で実施されます。
自己血輸血業務

自己血採血
自己血輸血は,手術中の出血に備え,予め自分自身の血液を手術前に採血して保管しておく輸血方法です(術前貯血式自己血輸血)。自己血輸血では,同種血(日赤血)の輸血による副反応を防止することは出来ますが,患者さんからまとまった量の採血が必要なこともあり,注意深く実施する必要があります。当院の自己血輸血業務は,採血から保管管理まで一貫して輸血部により行っています。採血は専任医師と看護師により,保管管理は専門の臨床検査技師が行い安全に自己血輸血を遂行できる体制を構築しています。なお,自己血輸血は,手術のスケジュール,患者さんの状態などにより希望に添えない場合もあります。詳しくは,主治医にお尋ねください。
コンサルテーション業務
輸血は適正に行うよう法的に定められています(薬機法)。また,善意の献血で支えられていることなどより,不適正な輸血は厳に慎まなければなりません。輸血部では,個々の輸血の申し込みをチェックし,輸血が不要と思われる症例や,逆に申し込み量では不足すると思われる症例に対して,輸血部医師を中心に積極的に助言を行っています。輸血による副反応の発生時は,主治医と連携して原因究明に必要な検査を実施するとともに必要であれば治療に対する助言も行います。
造血幹細胞移植関連業務
白血病などの治療で実施される造血幹細胞移植には,骨髄移植,末梢血幹細胞移植,臍帯血移植があります。特に末梢血幹細胞移植は,全身麻酔の必要が無いこと,腫瘍の治療で行われる大量化学療法に併用される(自家末梢血幹細胞移植)ことなどより,症例が増加しています。輸血部では,専用の成分採血装置を使用して移植ドナーや患者さんから末梢血幹細胞を採取します。また採取した末梢血幹細胞液に含まれる造血幹細胞をフローサイトメトリー(目的とする細胞を蛍光色素で標識し,レーザー光を照射して蛍光強度などで細胞を分類する検査)という方法で測定し,移植に必要な細胞数が確保できていることを確認し,移植時まで安全に凍結保管します。

末梢血幹細胞採取室
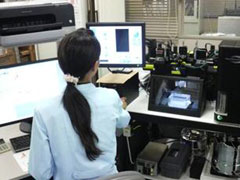
造血幹細胞の測定
その他(臨床研究等)
本院では,下記の研究を実施しています。この研究は,愛知医科大学医学部倫理委員会において,ヘルシンキ宣言の趣旨に添い,人を対象とする医学系研究に関する倫理指針,ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針等を遵守し,医の倫理に基づいて実施されることが審査され認められた研究です。
今回の研究は,対象となる患者さん一人ずつから直接同意を得て行う研究ではなく,研究内容の情報を公開し,研究対象者となることを拒否できる機会を与えることが求められているものです。もし,この研究に関するお問い合わせなどありましたら,以下の「問い合わせ先」までご連絡ください。
| 研究課題名 | 輸血医療におけるトレーサビリティ確保に関する硏究 |
|---|---|
| 研究機関名 | 愛知医科大学病院 |
| 研究機関の長 | 病院長 天野 哲也 |
| 担当科等 | 輸血部 |
| 研究責任者 | 客員教授 加藤栄史 |
| 試料・情報を利用する学外の研究機関名・研究責任者名 | 国立感染症研究所 客員研究員 松岡佐保子 東京大学 教授 岡崎仁 日本赤十字社 本部長 紀野修一 日本赤十字社 安全管理課長 日野郁生 日本赤十字社 技術部次長 後藤直子 熊本大学病院 客員教授 米村雄士 熊本大学病院 助教 上野志貴子 北里大学医学部 講師 大谷慎一 東京医科大学八王子医療センター 准教授 田中朝志 福島県立医科大学 博士研究員 北澤淳一 佐賀大学 教授 末岡榮三朗 |
| 研究の意義・目的 | 血液製剤の輸血によって生じるアレルギー反応や発熱などの副作用は,その実態や原因の多くがわかっていません。本研究では,日本における血液製剤の使用の実態や,輸血による副作用の実態を調査・解析することで,輸血の安全性・安全供給の向上を目指します。 |
| 対象となる患者さん | 硏究前年度(平成30年度の硏究の場合:平成29年4月1日〜平成30年3月31日)に当院を受診し,血液製剤の輸血を受けた患者さん |
| 研究の方法 | 血液製剤を製造している日本赤十字社の持つ血液製剤とその献血をされた方のデータと,輸血を実施した医療機関の持つ血液製剤とその輸血を受けた方のデータを,個人情報を除いた形で抽出し,血液製剤の製剤番号で連結して解析することで,輸血の実態を調査します。 当院が提供する情報は,血液製剤のデータ(製造番号,種類,当院に納品された日,使用または廃棄日)と,その輸血を受けた方のデータ(血液型,性別,年齢,輸血による副作用の有無と副作用の種類)です。新たに加わる身体的および経済的,医療的負担はありません。 本硏究について目的を含めて硏究の実施についての情報を本院輸血部のホームページ上で公開します。 |
| 研究期間 | 倫理審査承認日 ~ 2027年3月31日 |
| 研究に用いる試料・情報 | 情報:血液型,性別,年齢,輸血による副作用の有無と副作用の種類など |
| 外部への試料・情報の提供 | 本研究は,国立感染症研究所が主導する多施設共同研究で,国立感染症研究所倫理委員会および愛知医科大学病院倫理委員会より承認を得ております。当院が提供したデータは,国立感染症研究所に送られ,多施設からのデータが集められてデータベースを形成します。国立感染症研究所で,そのデータベースをもとに解析を実施します。 |
| 試料・情報の利用又は提供を希望しない場合 | 本研究への試料・情報の利用又は提供を希望しない方は,下記問い合わせ先まで申し出てください。 |
| 問い合わせ先 | 愛知医科大学病院 輸血部 担当者:客員教授 加藤栄史 〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1 電話0561-62-3311(内線77671) |
キーワード
輸血部,血液型検査,輸血,造血幹細胞移植,自己血,適正輸血,輸血副作用