-
〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1
TEL : 0561-62-3311
構内全面禁煙 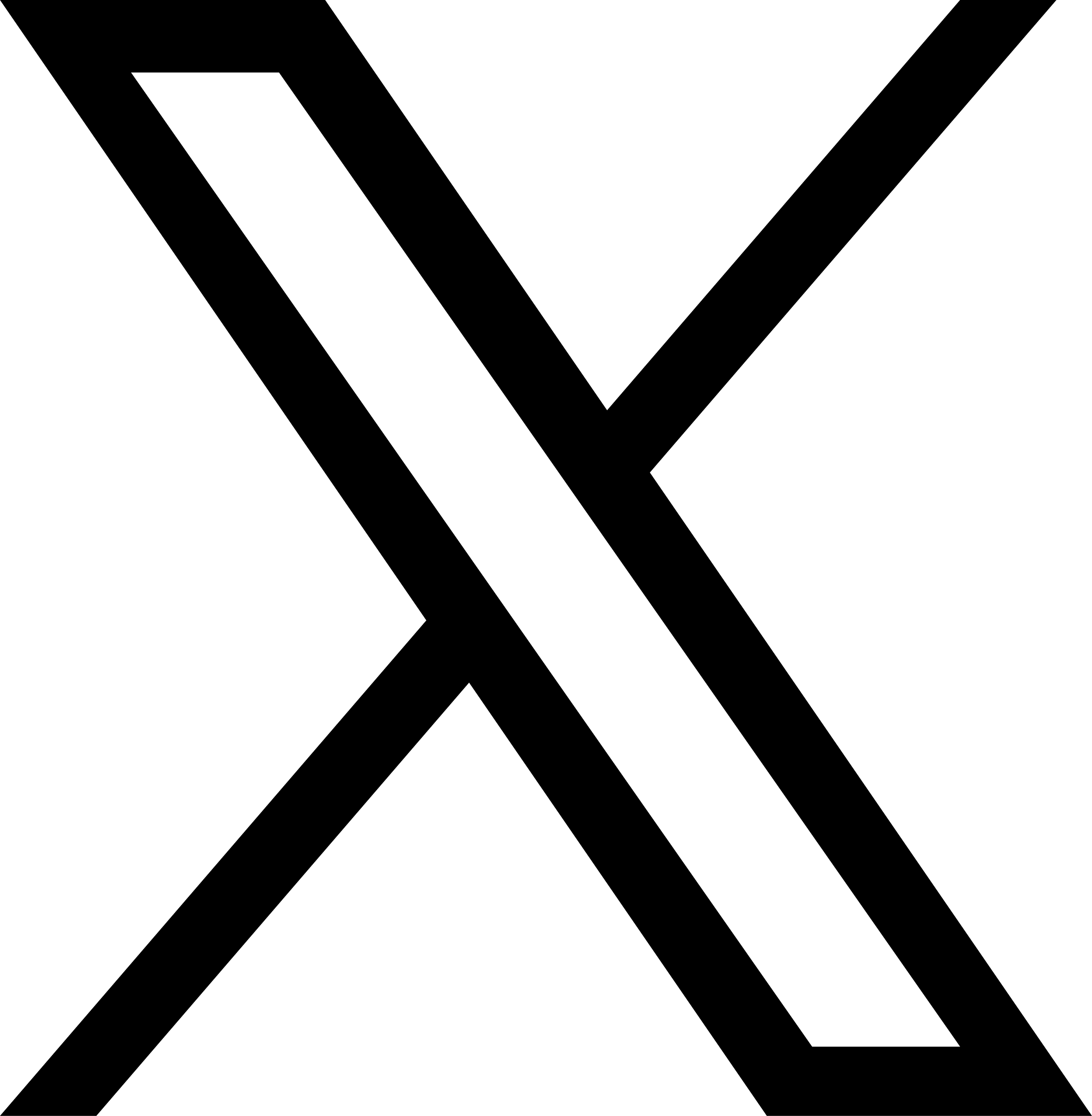
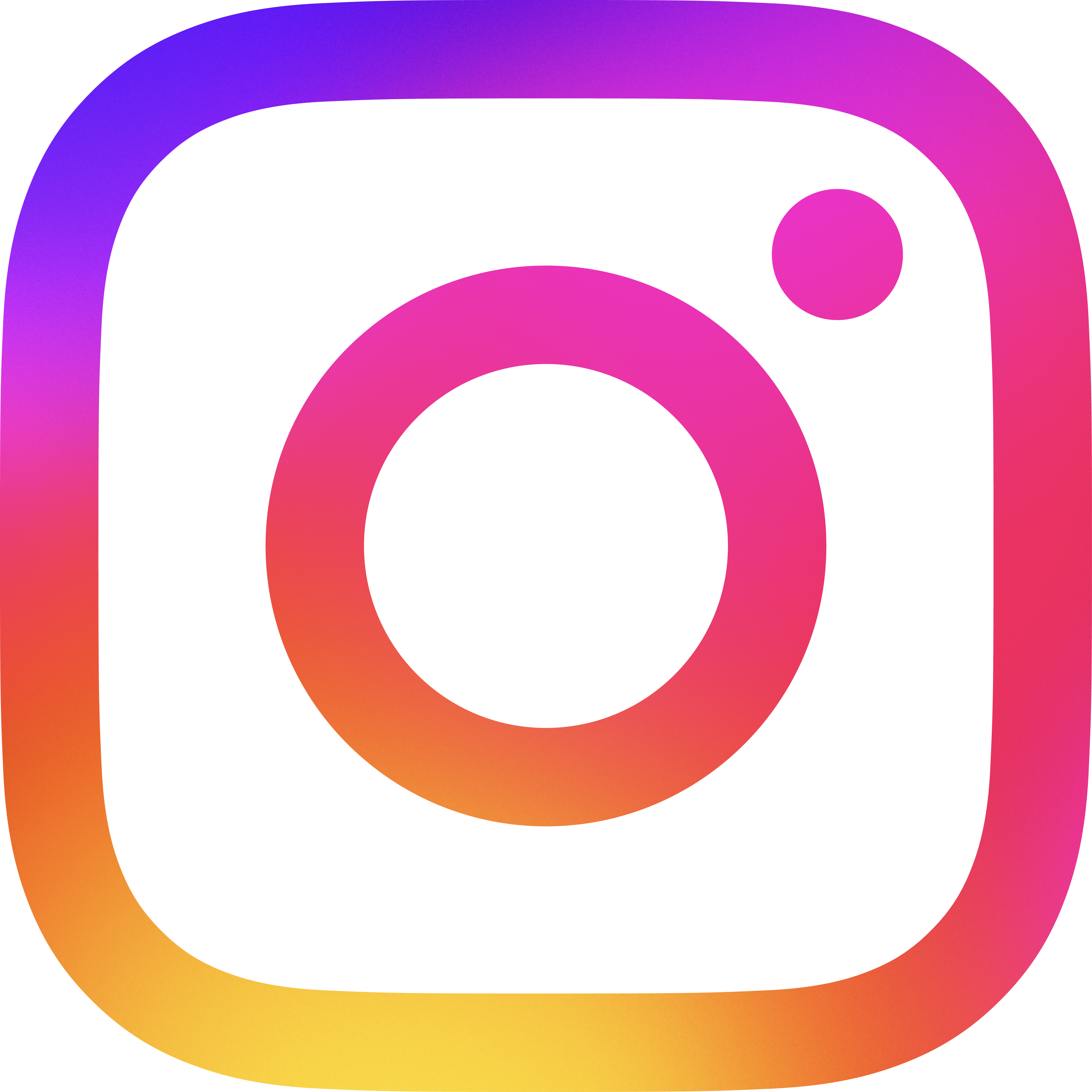
令和7年度老人保健健康増進等事業
本学が応募申請した事業が,老人保健健康増進等事業に採択されました。
事業概要
| 事 業 名 | 広域的長期浸水(湛水)・液状化被害による長期孤立が予測される海抜ゼロメートル地帯における災害時福祉医療連携ネットワークモデルの作成を目指した調査研究事業 |
|---|---|
| 事業目的 |
海抜ゼロメートル地帯は,南海トラフ地震などの大地震で液状化が発生しやすく,地盤沈下や津波浸水の長期化,孤立,生活環境の悪化が懸念される地域である。特に高齢者介護施設では,入所者の健康悪化や災害関連死の増加が重大な課題である。 これまでの調査研究においては,高齢者施設と自治体等が迅速に情報を共有する体制を整備することが重要であるとされた。このため,災害時保健医療福祉情報連携ネットワークシステム(通称:DH-Wins)をアプリ開発し,施設の被災状況や備蓄情報を即時に共有できる仕組みを構築した。実証訓練では一定の成果を得たが,対象地域や災害種別が限定される課題が明らかとなった。 本事業では,DH-Winsの改良・普及とともに,標準的な情報共有体制の強化を進め,災害時に円滑な施設避難や物資支援を実現することを目的とする。また,これらの知見をもとに厚生労働省の災害時情報共有システムを更に補完できるものとして改修し,全国普及を図り,より実効性の高い情報共有基盤の整備につなげることを目指すものである。 |
| 事業概要 |
|
| 事業期間 | 令和7年6月13日から令和8年3月31日まで |
| 検討委員会 |
第1回:令和7年7月11日(金) 第2回:令和8年2月13日(金) |
| 普及啓発研修 |
<高齢者施設 災害対応研修> ~命をつなぐ情報共有とBCP強化~
|
| 実証訓練 | 令和8年1月21日(水) |
令和6年度老人保健健康増進等事業
本学が応募申請した事業が,老人保健健康増進等事業に採択されました。
事業概要
| 事 業 名 | 広域的長期浸水(湛水)・液状化被害による長期孤立が予測される海抜ゼロメートル地帯における災害時福祉医療連携ネットワークモデルの作成を目指した調査研究事業 | ||
|---|---|---|---|
| 事業目的 | 能登半島地震支援経験から,令和5年度の老健事業にて提言した「迅速かつ的確な物品補給,避難・籠城支援のための高齢者介護施設,市町村,都道府県,医療機関も含めた情報共有体制を整備」するため,長期広域孤立が予測される海抜ゼロメートル地帯をモデル地域とし,1. 市町村・高齢者介護施設・医療機関を中心とした検討委員会の設置,2. 災害時組織連携体制における情報発信・共有体制整備,3. 効果的支援体制確立に向けた事前準備内容確立,4. 実証訓練にて検証することにより,平時における施設機能の把握・共有内容,役割分担を明確化するとともに,公助・共助機関が一体となった災害時福祉医療連携ネットワークモデルを構築し,全国普及を図る。 | ||
| 事業概要 |
|
||
| 事業期間 | 令和6年9月26日から令和7年3月31日まで | ||
| 担当部署 | 災害医療研究センター(津田雅庸,小澤和弘,高橋礼子,柴田隼人,川谷陽子,牧野久美子,岡田万由子,阪本友美子) | ||
| 実証訓練 | 【目 的】 南海トラフ地震最大想定時に本年度事業で能登半島地震での高齢者介護施設被災対応をも参考として検討した「情報発信・共有体制の確立」のための情報収集様式・一覧表及び情報共有システムを始めとした情報伝達方法の有効性を検証し,効果的支援を行うための役割分担,情報共有方法,支援方策を検討することを目的とする。 【開催日】 令和7年1月24日
|
||
| 事業成果 | ~ 災害時保健医療福祉情報連携ネットワークシステム (略称:D H-W ins)行動計画の作成とアプリ開発 ~ |
||
 令和6年度の調査研究事業では,海抜ゼロメートル地帯の市町村及び高齢者介護施設職員で構成した検討委員会を設置し,能登半島地震の支援経験、令和4・5年度老人保健健康増進等事業から得た知見を踏まえ,施設・市町村・県が連携した支援体制のあり方を検討し,公助・共助機関が一体となった地域全体の介護・医療機能の継続を行うべく「災害時保健医療福祉情報連携ネットワークシステム」を作成し,実証訓練による検証結果から,「災害時保健医療福祉情報連携ネットワークシステム行動計画」を作成した。 |
活動実績
活動報告
南海トラフ地震等激甚災害では,被害が広域的かつ甚大となり,海抜ゼロメートル地帯などの低地では浸水した津波が滞り,ライフライン供給も途絶することが予測され,その地域に所在する高齢者介護施設等は 長期間の孤立状態となり,早急な公的支援が求められる。
このような背景から,令和6年度調査研究事業では,効果的支援が行える「災害時福祉医療連携ネットワークモデル」構築を目指し,愛知県西部海抜ゼロメートル地帯を対象にモデル地域として各活動に取り組んできた。
本事業では,海抜ゼロメートル地帯の市町村,高齢者介護施設職員及び医療機関による検討委員会・作業部会を設置し,災害時組織連携体制,アプリを活用した情報発信・共有体制,効果的支援体制確立に向けた事前準備内容を検討し,開発した情報収集・集計プログラムについて実証訓練を踏まえて検証し,能登半島地震支援状況,令和4・5年度老人保健健康増進等事業から得た知見を踏まえ,公助・共助機関が一体となった地域全体の介護・医療機能を継続するため,情報共有体制確立を目指す「災害時保健医療福祉情報連携ネットワークシステム(D H-W ins)」を作成した。
D H-W insでは,施設がBCP,防災マニュアル行動計画に基づき収集した施設の人的・物的被害情報をアプリ機能による集計後,要避難者,要医療者を選定するとともに施設として避難,籠城,業務継続かの方針を決定し,市町村,都道府県と情報共有をし,市町村・都道府県が支援方針を確認し,医療搬送先,避難先,避難方法,物品支援等の支援が行われる構成としている。
令和5年度老人保健健康増進等事業
本学が応募申請した事業が,老人保健健康増進等事業に採択されました。
事業概要
| 事 業 名 | 海抜ゼロメートル地帯における洪水・高潮・津波災害時を想定した南海トラフ地震時の高齢者介護施設を中心とした広域避難及びBCPに関する調査研究 |
|---|---|
| 事業目的 |
令和4年度老人保健健康増進等事業において実施した,海抜ゼロメートル地帯の高齢者介護施設の実態調査では,津波・高潮・洪水災害における浸水は期間が長く(湛水),一時的な垂直避難により避難するも,多くの高齢者介護施設は施設内環境悪化により,利用者の健康状態は悪化し災害関連死が多く発生することが危惧され,市町村を始めとした行政機関,救出救助関係機関,医療機関,DMAT・DCATを始めとする支援機関が地域連携した広域的避難・支援が求められた。 これらの対策として,発災前から復興までの海抜ゼロメートル地帯における地域連携方策を組み入れたBCP指針を作成することを目的とする。 |
| 事業概要 |
|
| 事業期間 | 令和5年6月8日から令和6年3月31日まで |
| 担当部署 | 災害医療研究センター(津田雅庸,小澤和弘,高橋礼子,柴田隼人,牧野久美子,岡田万由子,杉下陽子) |
| シンポジウム |
海抜ゼロメートル地帯における地域BCPに関するシンポジウム (令和6年2月15日開催) |
活動実績
活動報告
広域的・長期的に甚大な被害を受ける海抜ゼロメートル地帯では,施設だけでの対応は困難で,広域的地域BCPの作成が求められる。
このことから,海抜ゼロメートル地帯を広域に有する愛知県西部をモデル地域として,関連市町村,高齢者介護施設及び医療機関で検討委員会を設置し,南海トラフ地震の被害想定に基づき机上演習を行い,各機関の行動計画,BCPの課題を抽出・検討し,また,令和6年1月に発生した石川県能登半島地震の支援活動経験も含めたシンポジウムを開催することにより,それらの検討結果をもとに「海抜ゼロメートル地帯における地域BCPのあり方」をとりまとめた。
提言した地域BCPを実効性のある地域BCPとするためには,海抜ゼロメートル地帯に属する高齢者介護施設,市町村だけでなく都道府県,医療機関等関係機関も含めて更なる検討が必要であり,災害時組織体制,タイムライン,情報共有体制,物品支援体制,避難・籠城方法を広域的に整備していくことが重要である。
令和4年度老人保健健康増進等事業
本学が応募した事業が,老人保健健康増進等事業に採択されました。
事業概要
| 事 業 名 | 海抜ゼロメートル地帯における南海トラフ地震時情報,気象災害特別警報発令時の高齢者介護施設の対応に関する調査研究 |
|---|---|
| 事業目的 |
海抜ゼロメートル地帯(以下「ゼロメートル地帯」という。)における被災では,津波・高潮・洪水による長期浸水(以下「湛水」という。)が生じ,多数の施設環境悪化は長期化し,業務継続が困難になることから,被災前からの事前避難基準を含めた業務継続計画(以下「BCP」という。)の作成が必要である。 このことから,ゼロメートル地帯を広域に有する濃尾平野市町村をモデル地域とし,高齢者介護施設,市町村,保健所,医療機関による検討委員会を設置し,各施設に対するアンケート調査・分析を行い,南海トラフ地震時情報,気象災害特別警報発令時における湛水地域内高齢者介護施設用BCPモデルを作成するとともに,各施設に対する普及を図ることを目的とする。 |
| 事業概要 |
|
| 事業期間 | 令和4年6月6日から令和5年3月31日まで |
| 担当部署 | 災害医療研究センター(津田雅庸,小澤和弘,高橋礼子,牧野久美子,岡田万由子) |
| 研 修 会 |
海抜ゼロメートル地帯高齢者介護施設BCP研修会 (令和5年3月14日開催) |
海抜ゼロメートル地帯高齢者介護施設BCP研修会
愛知医科大学災害医療研究センターでは,令和4年度老人保健健康増進等事業として,海抜ゼロメートル地帯に位置する高齢者介護施設の減災策調査研究事業の採択を受け,事業を進めてまいりました。
この度,同事業の調査研究のまとめとして,「海抜ゼロメートル地帯高齢者介護施設BCP研修会」を開催しました。
| 開 催 日 | 令和5年3月14日(火) |
|---|---|
| 時 間 | 13時00分~16時30分 |
| 場 所 | 東別院会館3階 東別院ホール |
| 内 容 |
我国において海抜ゼロメートル地帯を広域に有する濃尾平野にある高齢者介護施設の被害を調査研究し,多くの施設が津波・高潮・洪水浸水により長期間継続して孤立することが判明したことから,それに対応するためのBCPを作成しました。 このたび作成したBCPを各介護施設に普及することを目的とした研修会において,南海トラフ地震臨時情報巨大地震警戒発令時,気象情報レベル3での事前避難を組込んだBCPの呈示,長野県台風19号にあった高齢者介護施設の業務継続例の報告,備蓄資機材展示・バーチャル映像による被災体験を実施 |
| 動 画 |
当日の研修会の様子はこちら(YouTube) |
活動実績
活動報告
海抜ゼロメートル地帯における被災では,津波・高潮・洪水による長期浸水(以下「湛水」という。)による孤立が生じ,多数の施設環境悪化は長期化し,高齢者介護施設利用者の災害関連死発生のリスクが高くなることから,被災前からの事前避難基準を含めた海抜ゼロメートル地帯向け業務継続計画(以下「BCP」という。)の作成が求められる。
このことから,海抜ゼロメートル地帯を広域に有する濃尾平野市町村をモデル地域とし,高齢者介護施設,市町村による検討委員会を設置し,高齢者介護施設ハザードマップの作成による施設被害想定,各施設に対するアンケート調査・分析,介護施設が被災した現地調査を行い,南海トラフ地震時情報,気象災害特別警報発令時を含めた湛水地域内高齢者介護施設用BCPモデルを作成するとともに,研修会の実施により各施設に対する普及を図った。
令和元年度老人保健健康増進等事業
昨年度に引き続いて,本学の応募した事業が老人保健健康増進等事業に採択されました。
今年度については「生活不活発病」を始めとする震災関連死の低減に向けて,様々な事業を実施していく予定です。
事業概要
| 事 業 名 | 災害時に懸念される『避難生活に起因する生活不活発病』予防のための知見の集約と地域における普及啓発モデル事業 |
|---|---|
| 事業目的 | 行政,保健医療福祉機関,地域コミュニティ,学識経験者で構成された「災害時を想定した地域ネットワーク検討委員会」を設置し,検討委員会の中で被災地域の実態調査,文献調査するとともに,過去の災害(新潟中越地震,東日本大震災等)から考察した生活不活発病に関する文献を引用し,各機関の行動マニュアルの作成,研修会・訓練を実施し,具現化を図る。更に,その行動計画を地域における普及啓発モデルとして全国に発信する。 |
| 事業概要 |
|
| 事業期間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで |
| 担当部署 | 災害医療研究センター(加納秀記,津田雅庸,小澤和弘,高橋礼子,北川晃子,岡田万由子,田中綾子) |
| 委 員 会 | 災害時を想定した地域ネットワーク検討委員会 |
大規模災害時対応減災総合連携訓練
令和2年3月21日(土)に開催を予定しておりました「大規模災害時対応減災総合連携訓練」につきましては,新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を踏まえ,やむを得ず開催を中止することとしますのでご案内致します。
お申し込み頂きました方々につきましては,ご理解の程,宜しくお願い申し上げます。
愛知医科大学では,厚生労働省の老人保健健康等増進事業の採択を受け,今年度については「生活不活発病」を始めとする震災関連死の低減に向けて,様々な事業を実施しております。
この度,保健医療福祉機関・行政・地域住民に対する機関別の「大規模災害時対策減災研修」のまとめとして,総合連携訓練を実施しますので,受講を希望される方は,次のとおり申込ください。
| 開 催 日 | 令和2年3月21日(土) |
|---|---|
| 時 間 | 13時00分~17時00分 |
| 場 所 | 愛知医科大学本館2階たちばなホール・講義室・セミナー室 |
| 内 容 | 南海トラフ地震等巨大地震想定として,一人でも被害を軽減するために長久手市・医療施設・福祉施設・地域住民がそれぞれの立場での行動,それぞれの連携活動を習得するため,仮想避難所,仮想市役所,仮想医療福祉施設を設置し,模擬体験連携訓練を行います。 |
| 申込期間 | 2月17日(月)~3月6日(金) |
| 付 記 | 受講希望者が多数の場合は,見学のみとなることがありますので,ご了承ください。 災害等の社会状況を考慮し,訓練を中止する場合は,ホームページにてお知らせします。 |
| 問合せ先 | 老健事業事務局(北川:0561-76-3029,谷:0561-63-1063) |
活動実績
活動報告
愛知県長久手市をモデルとして行政,保健医療福祉機関,地域コミュニティ,学識経験者で構成された「災害時を想定した地域ネットワーク検討委員会」を設置し,検討委員会の中で保健医療福祉機関・行政・地域コミュニティの連携強化,文献調査の結果から生活不活発病予防のためには避難生活の環境維持と考察したことから,避難生活環境の劣悪化を防ぐことを趣旨として中越・中越沖地震被災の新潟県,東日本大震災における岩手県を視察調査し結果も踏まえて関係機関の行動指針を作成した。
作成した行動指針については,地域住民,保健医療福祉機関に普及啓発するために研修プログラムを作成し,研修会を実施した。
平成30年度老人保健健康増進等事業
事業概要
| 事 業 名 | 災害時を想定した視点からの地域ネットワークモデル事業 |
|---|---|
| 事業目的 | 災害時における地域コミュニティ強靭化の必要性及び事例報告等は,東日本大震災・熊本地震でも散見されるが,体系的な調査研究は進んでいないのが現状である。 本事業では,防災・減災を意識した地域包括ケアシステム及び災害に備えた地域コミュ二ティの強靱化について検討し,その案件をまとめ公表することで,全国の自治体に対して「地域コミュニティの強靭化を含めた地域包括的ケアの確立」に向けた方法論として発信することを目的とする。 |
| 事業概要 |
高齢者などが可能な限り住み慣れた地域社会で,自分らしい暮らしが続けられる「地域包括システム」の構築に向けて全国の市町村で取組が進んでいる。しかし,この地域包括ケアシステムは,現時点で「平時」における取組に留まっており,災害発生時や災害に備えてのシステムにはなっていない。 また,厚生労働省告示の中で平成30年度から開始する,第7期市町村介護保険計画の策定等に際して,防災担当部局との連携に努めるよう自治体に求める記述はあるものの,地域の実情に応じた取組に委ねられており,具体的な方法論は明らかになっていない。 更に,30年以内に70~75%で発生するといわれる南海トラフ地震では,死傷者・避難者が多数発生するだけでなく,医療機関・介護保険施設等の被災も予想され,ひいては地域コミュニティそのものも危機的状況に陥ると考えられる。 災害時における地域コミュニティ強靭化の必要性及び事例報告については,東日本大震災・熊本地震でも散見されるが,体系的な調査研究は進んでいないのが現状である。 そこで,南海トラフ地震及び津波による被害が想定される東海地方において,防災・ 減災を意識した地域包括ケアシステムや地域コミュニティの強靭化について検討し,その案をまとめで公表することで,全国の自治体に対して「地域コミュニティの強靭化を包含した地域包括的ケアの確立」に向けた方法論として発信していきたい。(高齢者等を念頭においた防災・減災のコミュニティづくり) |
| 事業期間 | 平成30年9月12日から平成31年3月31日まで |
| 担当部署 | 災害医療研究センター(加納秀記,小澤和弘,高橋礼子,北川晃子,岡田万由子,田中綾子) |
| 委 員 会 | 災害時を想定した地域ネットワーク検討委員会 |
活動実績
活動報告
南海トラフ地震の重点受援県に指定された愛知県の中で都市基盤化が整備された愛知県長久手市をモデル地区とし長久手市有識者で構成した「災害時を想定した地域ネットワーク検討委員会」を設置し,南海トラフ地震における保健・医療・福祉体制及び地域コミュニティのあり方を予測し,東日本大震災,熊本地震の被災地の実態調査,長久手市民の意識調査を行い,それらの結果から調査研究等報告書(災害時における地域ネットワークのあり方)を取りまとめた。また,災害時に必要な地域ネットワークの情報共有システムの検討も行った。調査研究等報告書(災害時における地域ネットワークのあり方)を取りまとめ後,長久手市住民,行政関係者,保健医療福祉関係者に対しての講演会で呈示及び提言し,参加者の承諾を求めるとともに具現化する取組について確認をした。
 お問合せ
お問合せ








