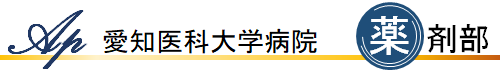チーム医療
栄養サポートチーム(NST:Nutrition Support Team)
NSTは、医師・薬剤師・看護師・管理栄養士・歯科医師・歯科衛生士・臨床検査技師などの多職種で構成された医療チームです。入院患者さんの栄養状態をチェックし、それぞれの専門知識を生かして、一人ひとりに見合った食事形態、栄養補助食品、点滴メニューなどの栄養療法を、主治医に対して提案しています。当院NSTでは、毎月約5000件のアセスメント回診を実施しています。その中で薬剤師は、輸液や経腸栄養剤の選択や使用方法のアドバイスを行ったり、栄養剤と薬の飲み合わせや副作用のチェックをしています。
緩和ケアチーム
緩和ケアチームは、医師・薬剤師・看護師・栄養士・歯科衛生士・理学療法士・作業療法士など多職種で構成されており、年間約5000件のチームラウンドを通じ、それぞれの専門性を活かしながら患者さんやそのご家族の様々な苦痛(つらい)症状の緩和に努め、質の高い療養生活が送れるようサポートしています。その中で薬剤師は、患者さんが感じている痛み・吐き気・呼吸苦・不眠などのつらさを正しく評価したうえで、薬学的観点から最も適切に薬物治療が行われるようサポートしています。入院患者さんへは少なくとも週2回ラウンドを行い、病棟薬剤師とも情報共有しています。外来患者さんへは、緩和ケア外来診療を週に4日、医師・看護師と共に行い、医療用麻薬を含めた最適な薬の使用方法についての情報提供も行っています。
また、月1回地域連携カンファレンスを行い、地域の医療機関のスタッフとも情報共有をしています。
抗菌薬適正使用支援チーム(AST:Antimicrobial Stewardship Team)・感染対策チーム(ICT:Infection Control Team)
AST・ICTは、医師・薬剤師・看護師・臨床検査技師・事務職の多職種で構成されています。その中で薬剤師はAntimicrobial Stewardship活動に特に注力しています。Antimicrobial Stewardshipとは、抗菌薬(Antimicrobial)使用の管理(Stewardship)を意味しています。血液培養陽性例、特定抗菌薬の使用例などの患者さんを対象としてASTラウンドを実施しています。ASTラウンドにおいては、抗菌薬の選択や投与設計、さらに抗菌薬使用に関わる診断についても提言することで感染症の診療支援を行っています。さらに、必要に応じて患者さんのベッドサイドに行き、主治医と診療方針について直接協議も行っています。当院では年間約6000件のASTラウンドを実施しています。
また、ASTであると同時にICTのメンバーとして、診療支援に関することだけでなく、感染伝播防止など感染対策全般について、多職種と協力することで総合的な感染制御に取り組んでいます。
糖尿病療養支援チーム
生活習慣と社会環境の変化に伴い、糖尿病患者数は急激に増加しています。糖尿病は適切に治療をしないと様々な合併症が生じ、患者さんのQOLの低下のみならず生命の危機にもつながります。糖尿病には患者さんの病態や生活習慣にあわせた個別の指導と治療が必要なため、当院では医師・薬剤師・看護師・栄養士・臨床検査技師・理学療法士・歯科衛生士などで糖尿病療養支援チームを構成し、診療を行っています。
薬剤師は、お薬の説明や自己注射の指導を行い、他の職種と協力し糖尿病治療における自己管理の大切さを伝えています。また、糖尿病教室の開催や世界糖尿病デー(毎年11月14日)のイベントへの関わり、医療スタッフに向けたセミナーの開催を行っています。
褥瘡対策チーム
褥瘡(じょくそう)とは一般的に「床ずれ」と言われており、寝たきりなどによって、体重で圧迫されて血流が悪くなったり滞ることで、 皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまうことです。
褥瘡対策チームは医師・薬剤師・看護師・管理栄養士・理学療法士等の多職種によって構成され、各専門分野がアプローチを行い、総合的な褥瘡発生防止策を検討しています。その中で薬剤師は、カンファレンスや回診で褥瘡の病態を観察し、治療に使用する外用薬やドレッシング材(創傷被覆剤)について、その特性を活かした選定・使用法を提案・指導・評価を行っています。また、外用薬に限らず、患者さんの使用している薬剤を確認し、褥瘡発生の予防に努めています。さらに院内研修会も開催し、知識の共有も図っています。
呼吸療法サポートチーム(RST:Respiratory Support Team)
RSTとは酸素吸入や人工呼吸などの呼吸療法が必要な患者さんをサポートするチームで、医師・薬剤師・看護師・理学療法士・臨床検査技師・歯科衛生士などで構成されます。呼吸療法を受けられている患者さんのところへ回診を行い、病棟で適切な呼吸管理が安全に行えるように活動しています。呼吸生理へ影響を与える薬剤が使用される場合もあるため、薬剤師も回診に参加し薬物治療の観点からチームをサポートしています。各病棟に配置されているRSTリンクナースに対して勉強会を行い、様々な薬剤を使用している患者さんの、呼吸に関するリスクに気付いてもらえるようなスタッフ教育を心がけています。
医療安全管理室
医療安全管理室は、専任医師・兼務医師・専従看護師・専従薬剤師・専任事務職員・専従事務職員・警察OB職員の構成となっています。医療安全に関する各種研修会を開催すると共に、職員の医療安全への意識向上、医療安全に係る具体的方策の実施状況の確認及び周知徹底を目的に、年に2回の医療安全管理ラウンドを行っています。また、医療の質・安全を確保するために、各種医療の標準化を進めています。
禁煙外来
健康保険を使った禁煙治療では、12週間で5回の外来診察を行い、チャンピックス®という飲み薬、またはニコチネル®TTS®という貼り薬を使用します。それぞれ長所・短所があるので、患者さんに適したお薬を使います。
当院では2018年の禁煙外来開設時より、薬剤師も禁煙治療に携わっています。初回の診察では、薬剤師は禁煙補助薬の服薬指導と禁煙手帳の記載方法の説明を行い、2回目以降の診察では、医師の診察前に患者さんと面談し、服薬状況・副作用・禁煙状況を確認しています。面談の内容を医師・看護師と情報共有し、「禁煙したい!!」という方や「禁煙できる自信はないけど…。」という方へ多職種でサポートを行っています。