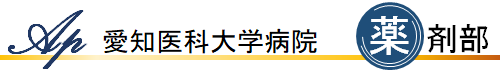部署紹介
服薬指導
患者さんにお会いしてお薬が正しく服用できているか、また、安全に薬物治療が行われているか確認します。
お薬のセット
お薬を朝昼夕毎にセットし、正しくお薬が飲めるようにしています。
他職種との情報交換
病棟に常駐し、患者さんのお薬についての情報等を医師や看護師と相談を行います。
急性期病棟での活動
ICU・HCUといった急性期病棟においても薬剤師は活動を行っております。
病棟(薬物療法支援室)
一般病棟
当院では、全病棟に専任の薬剤師を配置しています。入院患者さんの薬物治療のサポート、他の医療スタッフからの薬剤に関する相談、病棟の医薬品管理やリスクマネージメントに迅速に対応しています。
患者さんの持参薬、副作用・薬剤アレルギー歴、効果や副作用、コンプライアンスの状況、薬物血中濃度などを確認し、薬剤の投与量・相互作用の有無・剤形が適しているかなどを評価しています。その評価を他の医療スタッフと情報共有しながら、より良い薬物治療を提供できるよう努めています。
主な業務内容
- 持参薬の確認と評価、処方提案
- 患者さん個々の全身状態を考慮した処方鑑査
- 患者さんやご家族への服薬指導
- 薬物療法における有効性、安全性の評価
- 医師・看護師等への情報提供・勉強会の開催
- カンファレンスや回診などに参加し、他の医療スタッフと情報共有
- 病棟薬剤師ミーティング(薬物療法などの知識の共有)
- 病棟常置薬の安全管理
急性期病棟
救急搬送された重症患者さんの全身管理を行うEICU(救急集中治療室)およびHCU(高度治療室)、周術期や院内発生重症患者さんの全身管理を行うGICU(周術期集中治療室)、早産児や疾患を持って生まれた新生児の急性期治療を行うNICU(新生児集中治療室)およびGCU(新生児回復治療室)などの急性期病棟にも専任の薬剤師を配置し、病棟業務にあたっています。医師、看護師、理学療法士、臨床工学技士など様々な職種と連携し、患者さんの治療を支援するため毎朝のカンファレンスやベッドサイドでのディスカッションに参加しています。集中治療・救急医療においては患者さんの状態が刻一刻と変化するため、こまめに患者さんの全身状態を評価し、迅速に有効で安全な薬物治療を提案する必要があります。
患者さんの状態が安定し一般病棟へ退室する際には、急性期病棟での薬物治療や急性期にやむなく中断されていた既往疾患に対する薬物治療等についての情報を退室先の担当薬剤師へ申し送り、切れ目のない薬物治療の提供を目指しています。
調剤室
調剤室では、外来・入院患者さんの内服薬、外用薬、注射薬を調剤しています。1日平均では外来の処方せん約1100枚、入院の処方せん約400枚の調剤を行います。医師、歯科医師から発行された処方せんの内容(飲み合わせ・量・飲み方・使い方など)が、適切であるかを確認し、不明な点については、医師に照会を行っています。
患者さん一人ひとりに適したお薬を安全かつ速やかにお渡しできるよう日々努めています。
おくすり窓口
おくすり窓口では、外来患者さんのお薬をお渡ししています。
患者さんが正しく服薬できるようにお薬の効果、使い方、注意点などをお伝えし、患者さんからのお薬に関する相談にも応じています。
また、窓口のとなりにはインスリン・吸入薬の使い方や抗がん剤の説明等でお時間をいただく場合に、安心して説明を受けることができるようプライバシーに配慮した個室の指導室をご用意しております。
注射室
注射室の主な業務は、注射薬の払い出しです。投与量・投与経路・投与速度・配合変化・相互作用・投与間隔などのチェックを行い、注射薬を患者さん毎に取り揃えて払い出しをしています。注射薬は一般的に効果が強く、血管内に直接投与するため、使い方などを間違えると生命に危険を及ぼすリスクが高いので、十分注意して払い出す必要があります。
ピッキングマシン
薬剤部には注射薬自動払い出し装置を2台配置しており、迅速な業務を遂行するとともに患者さんの1回施用毎に調剤することにより院内の医療安全にも寄与しています。薬剤を正確に補充するため、バーコード管理を行っています。
注射薬カートセット
入院患者さんを対象に注射薬を患者さん毎、1施用毎にカートセットをしています。取り揃えられた注射薬を2名の薬剤師により鑑査を行い、病棟へ供給しています。 また、当院ではSPD搬送チームによる効率的な搬送・供給を行っており、医療スタッフの負担を軽減しています。
製剤室
製剤室の主な業務は、院内製剤の調製と無菌室での高カロリー輸液(TPN)の混合調製です。院内製剤とは、患者さんの状態、病気の種類や程度、治療効果あるいは規格・包装単位等の理由により市販品では十分な対応ができない場合に、院内で製造する医薬品をいいます。調剤業務の効率化を支援すると共に(予製剤)、個々の患者さんの多様な病態やニーズに対応(特殊製剤)することであり、病棟や外来診療で使用される各種処置用医薬品等の調製も含まれます。
院内製剤支援システム
院内製剤は、個々の病院において調製され患者さんに処方される薬剤であるため、十分な安全管理が必要です。当院では、製剤原料や製剤品情報を総合的に管理する日本初の「院内製剤支援システム」を開発し、院内製剤の調製、払い出し、使用患者、製剤品使用成績等をシステムによって管理することで、製剤品の安全性確保に努めています。DI室(Drug Information:医薬品情報)
お薬は効果、副作用、使用するときの注意点などの情報があって、はじめて使用することができるため、お薬と情報は切り離せない関係にあります。お薬の効果を最大限に利用し、かつ、副作用を最小限に抑えるには、お薬に関する情報を収集し、分類、整理、評価そして選択することから始まります。DI室では医師、歯科医師、薬剤師、看護師など全ての医療従事者と患者さんへそれらのお薬に関する情報の提供を行うことで、適切な薬物療法の発展を図り、医療の向上と効率化に貢献しています。
また、薬剤部内での新しいお薬の勉強会の予定や、MRなどに対するヒアリングも行っています。その情報をもとに患者さん、および医師をはじめとする医療スタッフからのお薬に関する問い合わせにも対応しています。お薬による重大な副作用が発現したと疑われる場合には、情報を収集し、厚生労働省へ報告を行っています。
さらに、DI室はお薬の採用を審議する薬事委員会の事務局も行っており、電子カルテにおいて、お薬に関する情報のメンテナンスを行っています。
TDM(Therapeutic Drug Monitoring:薬物治療モニタリング)
TDMとは、治療効果や副作用に関する因子をモニタリングしながら、それぞれの患者さんに個別化した薬物投与を行うことをいいます。特に血液中の薬物の濃度と治療効果や副作用との間に関係が認められる薬物では、血中濃度を指標にして投与量の調整を行います。
当院では、TDM担当薬剤師が薬物の血中濃度をもとに、患者さんの病態、治療効果や副作用の発現状況などを考慮し、医師へ適切な投与方法の提案を行っています。入院患者さんの場合は状態を把握している病棟薬剤師と連携し、外来患者さんの場合は医師と直接協議しながら、個々に適した投与設計を行います。
また、患者さんの病態・各薬剤の特性を考慮した初期投与方法の提案、投与量の確認や血中濃度測定の依頼なども行っています。
- 抗MRSA薬(バンコマイシン、テイコプラニン、アルベカシン)
- アミノグリコシド系抗菌薬(ゲンタマイシン、アミカシン)
- 抗真菌薬(ボリコナゾール)
- 強心薬(ジゴキシン) これら以外についても医師からの依頼に応じて投与設計などを行っています。
手術室サテライトファーマシー
当院には、手術室が19室あり、年間約9000件の予定手術・緊急手術が行われています。手術室にはサテライトファーマシーが隣接しており、そこには薬剤師が3名常駐しています。手術室では麻薬・筋弛緩薬・向精神薬等の取り扱いに注意が必要な薬剤を使用するため、サテライトファーマシーの薬剤師がこれらの薬剤について適正に管理を行っています。
また、クリーンベンチを使用し、PCAポンプを用いた術後持続投与鎮痛薬や心臓外科手術で使用する心筋保護液等を無菌調製しています。多職種と連携し、医薬品の在庫管理や情報提供等、安全かつ円滑な手術を行うことができるよう日々業務にあたっています。
入退院支援センター
入退院支援センターでは、患者さんが入院前から退院後まで安心して適正な医療を受けられるようさまざまな支援をしています。入退院支援センターの薬剤師は、予約入院患者さんの常用薬や市販薬・サプリメント等の把握、薬剤管理状況の聴取、副作用・アレルギー歴の確認、手術・検査前中止薬の確認と説明を行っています。入院前から薬剤師が介入することで、入院後の適切な薬物療法につなげられるよう努めています。
また、在宅療養に移行する際には、在宅で継続可能な薬物療法を検討し、地域医療スタッフへ薬剤情報提供を行うなど、退院後も安心・安全に療養生活ができるよう支援しています。
化学療法室
抗がん剤調製室には、薬剤師が常駐しており、安全かつ適切ながん薬物治療を提供するために、スケジュール・投与量・血液検査データ・併用する飲み薬等の確認を行っています。調製時には、抗がん剤曝露予防のため、安全キャビネットと閉鎖式薬剤移注システム(BD PhaSeal®)を使用しています。また、鑑査システムを導入しており、医療過誤防止および業務負担の軽減を図っています。
外来化学療法室での活動
外来化学療法室においては、常駐のがん専門薬剤師を中心に治療を受けられる患者さんへスケジュール・飲み薬の説明、副作用確認等を行っています。また、患者さんが医師の診察を受ける前の時間を利用し、診察前面談にも取り組んでいます。面談で確認した服薬状況や副作用等を医師へ報告し、支持療法の提案も随時行っています。
医薬品管理室
医薬品管理室では、院内で使用する医薬品の購入、在庫、供給、品質管理を行っています。また、輸血用血液を除く血液製剤の購入および使用状況の管理なども行っています。院内で取り扱う医薬品・消毒薬・検査薬は約2000種類あり、大きな箱に入った輸液類から小さなアンプルまで形態はさまざまです。中には1瓶で約180万円もする医薬品もあります。そのため、医薬品管理室では医薬品が適切に供給・管理できるように努めています。
安定供給・在庫管理
医薬品管理室では、治療に不可欠な薬剤を安定供給する事が求められます。一方で、不適切な購入管理は不良在庫を発生させ医薬品の無駄や病院収益に損失を与えることになることから適切な管理が必要となります。
そこで医薬品管理室では、薬剤部門システムの処方データを物流システムに取り込むことによって処方量に応じた薬品購入を実現し、医薬品の購入管理の適正化および省力化を行っています。また、処方データを利用した薬品管理システムを導入することによって、医薬品を必要な数量だけ確保し、病棟、診療科、その他の部署へ供給しています。
麻薬・向精神薬の管理
麻薬・向精神薬は「麻薬及び向精神薬取締法」で取り扱いが厳しく規制されている医薬品です。 そのため医薬品管理室では、これらの医薬品の使用状況の把握、在庫管理、残薬の廃棄にいたるまで厳密に管理を行っています。
未承認新規医薬品等評価部門
未承認新規医薬品等評価部門は、2017年4月に特定機能病院における医療安全対策強化のために新たに設置されました。医薬品安全管理責任者(薬剤部長)を部門長、医療機器安全管理責任者を副部門長とし、医療機器安全管理副責任者である臨床工学部と中央放射線部の各技師長、医師、薬剤師を含めた計11名で構成されます。
各診療科から申請のあった当院で使用したことのない国内未承認の医薬品や医療機器(適応外使用や院内製剤などを含む)の使用に関し、必要性、有効性、安全性について検討し、未承認新規医薬品等評価委員会(医師および医療安全管理室の医師・薬剤師等で構成)の意見を参考に適否を決定します。さらに、それらが適正な手続きに基づいて使用されていたかどうかなども確認しています。